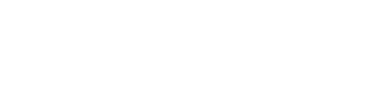これまで多くの仕事を通じていろいろな組織をみてきました。
組織や仕事がうまくまわるかは、なかで働くひとの能力次第だと思っていましたが、実はそれ以上に「適切な人員配置」が重要であるということを知りました。
能力とやる気に満ちた優秀なひと、能力はあるのに怠けることばかり考えるひと、やる気と情熱はあるのになぜかトラブルばかりを引き起こす人ひと、などなど。。。
だれをどこへ配置すれば組織はしっかりと機能していくのでしょうか?
今回は、ドイツの軍人ハンス・フォン・ゼークトが唱えた「意外」な組織論を取り上げつつ、適切なひとの配置について考察していきたいと思います。
やる気があるのは危険? 軍隊式組織論とは
ゼークトが提唱する組織論というのは、基本的に軍隊をベースとした考え方です。
一歩間違えればひとが死んでしまうシビアな世界だからこそ、ひとの配置についても妥協を許さない意外な観点が含まれています。
それでは、そのゼークトが提唱する4種類のモデルをみていきましょう。
①能力はあるのに怠けようとする者
適性:前線指揮官(現場のトップ)
基本的に自分自身は怠けたいため、部下の力を効率的に発揮することができる。どうすれば自分が楽に生き延びて部隊が勝利できるかを優秀な頭脳で考える。
能力があるのに怠けようとするひとは、現場では一番嫌われるタイプな気がしますが、実は組織にとっては重要な人材といえるのです。なんとなく高級官僚のイメージですね。
②能力がありマジメな働き者
適性:参謀(司令部で作戦を立てるひと)
能力がありさらに実務もこなして責任感があるため、司令官の右腕として働くことに向いている。一方、部下を率いて戦場に出ると、その責任感と実行力から自ら先頭に立ってしまい、結果的に部隊全体を危険に晒してしまう可能性も。
優秀な働き者がリーダーになると、周囲にも勤勉さと高い成果を要求するので、部下のやる気と自信はどんどん失われていきます。「名選手、名監督にあらず」という言葉がありますが、まさにこのタイプに当てはまります。
③能力がなく怠けようとする者
適性:総司令官(トップ)!? or 連絡将校、下級兵士(下っ端)
この4種類のなかで一番意外な内容のひとつが、無能な怠け者がトップに向いているという内容。
有能な参謀や司令官がいることが前提となるが、自ら考えて動こうとしないので参謀の進言どおりに動く。
あえて付け加えるならば、愛されキャラというか、人間性は優れている必要があるように感じます。能力がなく怠け者だけど、人間的な魅力があればトップに向いているということになります。
一方、無能な怠け者で、さらに人間的な魅力もない場合は、もはや下っ端になるしかないということです。
④能力はないもののやる気だけある者
適性:処◯(クビ)
そしてもう一つの意外な内容がこちら。恐らく日本の社会では評価される人材な気がしますが、戦場では処◯されてしまいます。
働き者ではあるが、無能であるために間違いに気づかずに実行してしまい、さらにそれを繰り返す。戦場では文字通り命とりとなる。
無能な働き者が最下位なのは、理解に苦しむ人が多いかもしれませんが、わたし自身、こういった人材が組織をダメにしていく例はたくさんみてきました。
最も最悪なのは、このタイプがトップに立ってしまうケースです。
よくあるのですが、運とやる気だけでたまたま成果を挙げてしまい、それが評価されてマネジャーに昇格するパターン…。
さあ、大変です。
本当は能力なんてないのに、過去の成功体験だけを頼りに、周囲に気合いとやる気を求めていきます。
まとめ
あなたがもし人事権を持っている立場ならば、この組織論を知っていて損はないと思います。
また、これらはなにも軍隊や会社組織だけに当てはまるものではなくて、町内会や各種サークル、主婦仲間や学生の集まりなど、ひとが集まってなにかを行う時にはある程度参考になる内容です。
もちろん、すべてがこの通りになるわけではないですが、特に若い人は知っておくと将来役に立つ可能性があります。
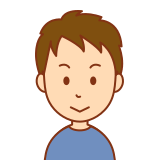
トップに向いているのは人間力があって能力とやる気のないひと
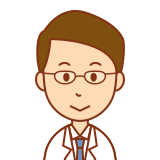
参謀に向いているのは能力とやる気のあるひと
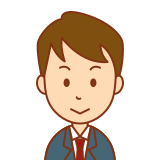
前線指揮官に向いているのは能力があってやる気のないひと
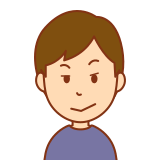
能力がなくてやる気のあるひとは…
えっ、ところでわたしはどのタイプかって??? 汗
一番上か、もしくは一番下、かもしれませんね。。。